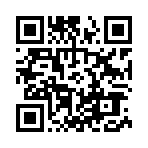2013年11月01日
公民館講座です
10月31日公民館講座を開催しました。
今回は
①「農薬がミツバチの大量死を引き起こしている!?」のビデオ鑑賞
②NPO会員井上氏による「喜界島の海からの恩恵はどこにいったのか」
の2本立てでした。
①は、今欧米各地で問題となっているミツバチ大量死の原因が農薬散布である、との研究報告がされてそれに対してEU・日本がどのような対応をしているかなどを記録したビデオです。
EUは「予防原則の理念」より、科学的に完全な立証はされていないが予防のため今から2年は禁止して、その間に科学的に立証するというスタンスです。
日本は、ほとんどの水田地帯で使っているこの農薬は、まだ完全に立証されたわけではないので今禁止にすることはできない、というスンタスでした。
この農薬の使用を完全に禁止すると農家に対してとんでもない損失がでるようです。しかし、自然界に何らかの影響を与えているのは間違いない(作物の種にこの農薬を1回コーティングすると、あとは何もしなくても虫が寄ってこないみたいです。そんな食糧危険すぎる)。
喜界島もこのジレンマの真っただ中です!
②は、井上氏が昔と今の海の変化を語ってくれました。
冒頭いきなり「ウニとナマコがいなくなった」で始まりました。確かに私も小さい時に、近所のおばちゃんに浅瀬で採れたウニを食べさせてもらった記憶があります。でも今はあまり見かけなくなりました。昔のような感じでは全くありません。井上さんは昔から潜って漁をするのですが、魚の量・珊瑚の数など海の恩恵が本当になくなってしまったと嘆いていました。
しかし、これも先ほどのハチと同じで陸上からの影響(農薬・除草剤・化学肥料・赤土など)が強いだろう、という範囲から出ることは難しいです。でも変わってしまったのは事実です。
それから講座の中で話がどんどん波及して、「トンボの種類が減った」「レンゲソウ、シロツメクサ、オオバコがなくなった」「キビ畑の朝顔が年々グレードアップしているので、除草剤もグレードアップせざる負えない」などなど・・・。
最後には、喜界島にはとにかく島中にゴミが多すぎる!!という話題にまでなりました。
先ほども書きましたが、喜界島は”今何とか生活する”と”未来の島のためにできること”のジレンマ(講座の後半では、そんなジレンマなど感じている人は少ないよ平気でゴミ捨てるもん、という人もいましたが)の真っただ中にいます。
島の良い未来を願わない人はいません。でも急に変えることは無理です。住民一人一人が意識を変えていかないと、という結論になりました。
今回の講座は時間をオーバーするという珍しい回になりました。


今回は
①「農薬がミツバチの大量死を引き起こしている!?」のビデオ鑑賞
②NPO会員井上氏による「喜界島の海からの恩恵はどこにいったのか」
の2本立てでした。
①は、今欧米各地で問題となっているミツバチ大量死の原因が農薬散布である、との研究報告がされてそれに対してEU・日本がどのような対応をしているかなどを記録したビデオです。
EUは「予防原則の理念」より、科学的に完全な立証はされていないが予防のため今から2年は禁止して、その間に科学的に立証するというスタンスです。
日本は、ほとんどの水田地帯で使っているこの農薬は、まだ完全に立証されたわけではないので今禁止にすることはできない、というスンタスでした。
この農薬の使用を完全に禁止すると農家に対してとんでもない損失がでるようです。しかし、自然界に何らかの影響を与えているのは間違いない(作物の種にこの農薬を1回コーティングすると、あとは何もしなくても虫が寄ってこないみたいです。そんな食糧危険すぎる)。
喜界島もこのジレンマの真っただ中です!
②は、井上氏が昔と今の海の変化を語ってくれました。
冒頭いきなり「ウニとナマコがいなくなった」で始まりました。確かに私も小さい時に、近所のおばちゃんに浅瀬で採れたウニを食べさせてもらった記憶があります。でも今はあまり見かけなくなりました。昔のような感じでは全くありません。井上さんは昔から潜って漁をするのですが、魚の量・珊瑚の数など海の恩恵が本当になくなってしまったと嘆いていました。
しかし、これも先ほどのハチと同じで陸上からの影響(農薬・除草剤・化学肥料・赤土など)が強いだろう、という範囲から出ることは難しいです。でも変わってしまったのは事実です。
それから講座の中で話がどんどん波及して、「トンボの種類が減った」「レンゲソウ、シロツメクサ、オオバコがなくなった」「キビ畑の朝顔が年々グレードアップしているので、除草剤もグレードアップせざる負えない」などなど・・・。
最後には、喜界島にはとにかく島中にゴミが多すぎる!!という話題にまでなりました。
先ほども書きましたが、喜界島は”今何とか生活する”と”未来の島のためにできること”のジレンマ(講座の後半では、そんなジレンマなど感じている人は少ないよ平気でゴミ捨てるもん、という人もいましたが)の真っただ中にいます。
島の良い未来を願わない人はいません。でも急に変えることは無理です。住民一人一人が意識を変えていかないと、という結論になりました。
今回の講座は時間をオーバーするという珍しい回になりました。
Posted by wakawaka at 22:05│Comments(0)
│イベント